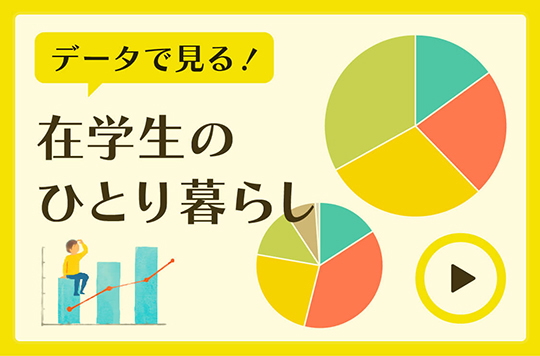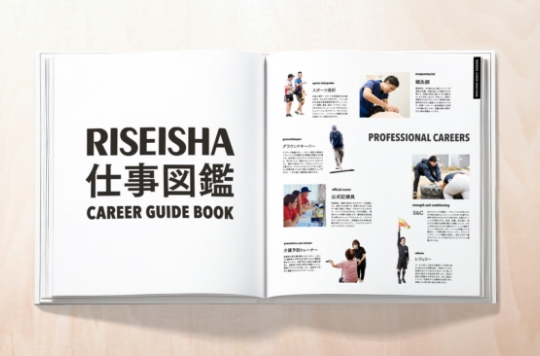09
佐藤 秀典 Hidenori Sato
外国語学科GM
「世界で勝つ」ためのマインドセット。
ラグビー日本代表の通訳から、専門学校の学科長へ。
グローバルスポーツの最前線を知る男は、
なぜ教育現場に身を投じたのか。
日本で唯一、スポーツ・医療と実践英語を組み合わせて学べる
外国語学科を立ち上げた舞台裏を、本人が語る。
2025年7月7日
2015年のラグビーワールドカップ・イングランド大会。ラグビー日本代表は34-32で強豪・南アフリカを撃破。「スポーツ史上最大の番狂わせ」と世界中から称賛された。続く2019年の日本大会では、アイルランド、スコットランドなどの強豪国を破り、初めてベスト8に進出した。
歴史に名を残したラグビー日本代表チームで通訳を務めていたのが、佐藤秀典だった。ヘッドコーチのエディー・ジョーンズ(’15)、ジェイミー・ジョセフ(’19)の最も近くにいる存在としてチームを支えた。現在は、履正社国際医療スポーツ専門学校・外国語学科のゼネラルマネージャー(GM)を務める一方、ラグビー国内最高峰リーグ「リーグワン」で通訳も務めている。
2020年に旗揚げした外国語学科。通訳、コーチ、トレーナー、スタッフなど、国際化の進むスポーツ業界で活躍できる英語人材を育成することをミッションとしている。佐藤は外国語学科の構想段階から独自のカリキュラム作成、立ち上げまですべてに携わった。自ら教壇にも立ち、第一線で得た経験と知識を学生たちに伝えている。

通訳の土台を作った「移住経験」
佐藤は1981年、東京都渋谷区で生まれ、二子玉川で育った。子どもの頃はサッカーが大好きだった。アルゼンチン代表、ディエゴ・マラドーナの全盛期だったこともあり、マラドーナ・モデルのプーマ製スパイクを履いて、多摩川の土手でボールを追いかけていた。
小学5年生で、家族とオーストラリア・ゴールドコーストに移り住むことになった。当時、観光で滞在していた日本人は多かったが、佐藤のように家族で完全に移住するケースはまだ珍しかったという。転入した学校のクラスで、アジア人は佐藤だけ。初めて自分が “外国人” になった瞬間だった。どうにか溶け込もうと、あえて陽気でオープンなキャラクターを演じて、自分から仲間の輪に入っていった。
現地に住んでいる中で、人種差別やいじめも経験した。第2次世界大戦時、旧日本軍はオーストラリア北部、ダーウィンを空襲した。高齢者世代にはその経験がある人がいて、家族を亡くした人も少なくなかった。日本人とわかると、態度を一変されることもあった。
「そんな環境だったから、幼いながらに『日本人ってなんなんだろう?』ということも考えました。そして、オーストラリアの文化に必死に順応しようとしました。思えば自分がやっている通訳は、監督やコーチの“言葉”にならないといけない。そのためには、その人たちのことを理解して、打ち解けないといけないですよね。だから当時の経験は今、確実に活きています」
「英語が話せるんだったら、手伝ってみたら?」
オーストラリアの高校を卒業後、佐藤は日本に帰国した。そして大阪有数の観光スポット・アメリカ村にあるシルバーアクセサリーショップで働き始めた。そこで、英語が話せることから海外買付けを任せられたのが通訳としての第一歩だった。アメリカへ出張し、現地のショップマネージャーと価格や購入個数などを交渉。あるときは日本の雑誌取材に同行して、インタビューの通訳を務めることもあった。
そういった経験から、佐藤は英語が武器になることを徐々に実感していった。また、オーストラリアで過ごしていたときに巡り合った、音楽のジャンルの一種、デスメタルにも傾倒し、大阪に拠点を置くデスメタルバンドのメンバーとしても活動した。
アメリカ村のショップでは、約4年間働いた。その後、自身のデスメタルバンド「INFERNAL REVULSION(悪魔的憎悪)」を結成。ヴォーカルを務め、本格的な音楽活動を開始しながら、パチンコ店のアルバイトや日雇いで生計を立てた。
そんなとき、「せっかく英語が話せるんだから、手伝ってみたら?」と、母が働いていた会社のラグビーチーム「ワールドファイティングブル(以降ワールド)」から誘いを受けた。チームのヘッドコーチはオーストラリア出身で、オージーアクセント(オーストラリア英語のアクセント)を披露すると意気投合。正式なオファーを受けて、チームに通訳として加入した。ここからスポーツ通訳としてのキャリアを歩み始める。
チームはバンド活動も許容してくれた。公式戦のない週末やシーズンオフには、レコーディングやライブの予定を詰めた。コーチや選手がライブに来てくれることもあった。2009年のワールド廃部までチームに所属し、以降はキヤノンイーグルス(現・横浜キヤノンイーグルス)に移籍した。
バンド活動は順調だった。日本のデスメタルバンドを代表するポジションまで駆け上がり、世界中の熱狂的なファンを獲得していった。2014年には、9カ月に及ぶワールドツアーが決定。それに伴ってキヤノンを退部し、ツアーに向けた準備を全力で進めた。
だが、ある日を境に、ツアープロジェクトの全体を仕切っていた業者からの連絡が途絶えた。蓋を開けてみれば、ツアーそのものが業者のトラブルで白紙になっていた。
「途方に暮れました。ワールドツアーはすでに公表していたし、それに備えてメンバーもみんな準備していて。うわぁ、どうしようって」
佐藤にある人物からメッセージが入ったのは、その数日後だった。ラグビー日本代表のヘッドコーチ、エディー・ジョーンズだった。
「通訳のポストが空くから、面接を受けてみないか?」
ジョーンズとはキヤノンでの仕事を機に知り合い、交流があった。通訳として佐藤を評価していたジョーンズは、偶然にもこのタイミングでオファーを出したのだ。佐藤は二つ返事で大阪から東京に飛んだ。
もしここで投げ出したら、それは一生ついて回る。
指定された面接場所は、都内のナショナルトレーニングセンターだった。2月の真冬にもかかわらず、緊張でダウンの下は汗だく。何を聞かれるのだろうか。焦りが止まらなかった。
だが、予想に反して、面接は2分にも満たない時間で終わった。
「実際に会って、僕の目を見て、確かめたかったんでしょうね。『一緒にワールドカップでやらないか』『やります』『じゃあ契約面はマネージャーと話して』。会話はこれくらいでした」
通訳になることをバンドメンバーも受け入れてくれ、佐藤は日本代表のスタッフとなった。その時点で、ワールドカップまでおよそ半年だった。
佐藤には激務がのしかかった。早朝のトレーニングに始まり、夜、寝床につくまで、通訳はヘッドコーチと常に行動を共にしなければならない。チームのトレーニングやミーティングはもちろん、取材対応、講演、ラグビースクールや学校でのイベント。休みはほとんどなかった。
仕事は「通訳」という言葉の範疇に収まらず、佐藤はまさにエディー・ジョーンズの側近だった。
「別々の場所にいたとしても、携帯は鳴りっぱなしで。『この資料作ってくれ』『これ買ってきてくれ』『あれを伝えておいてくれ』。働いた半年間は常に臨戦態勢で、丸々一日のオフがもらえたのは二日ぐらいでした」
なぜ、そんな激務に耐えることができたのか。
「やっぱりゴールが明確だったからです。半年先のワールドカップまで頑張ろうっていうみんなの結束力がすごかったんですよね。あとは、もしここで自分が投げ出したら、それは一生ついて回るんだろうなとも思っていました。白紙になったワールドツアーのこともあって、後にも引けない状況だったので、覚悟はありましたね。エディーさんからも『今はキツイと思うけど、ワールドカップで絶対にみんなの価値が上がるから、それまで我慢してくれ』って言われていて。南アフリカに勝って、本当にそうなったので、すごい人だなと(笑)」

’15年のワールドカップ後、日本代表のヘッドコーチにはジェイミー・ジョセフが就任した。通訳として続投した佐藤が新体制で苦労したのは、ヘッドコーチが変わることにより、文化や認識のすり合わせを新たにすることだった。
前任のジョーンズ体制では、選手たちの食事やミーティング、昼寝の時間まで全てが細かく決められ、管理されていた。だがジョセフは、選手たちが自ら考えて動く自主性を求めた。指揮官が代わったことによって生まれたギャップを解消していくのは、ジョセフの言葉を伝える佐藤の仕事だった。
「例えば食事前後のミーティングは、キャプテンやリーダー陣が自発的に進行していってほしいというのがジェイミー・ジョセフ流。でも、当初はそれが選手にうまく伝わっていないことが多くて、食い違いや衝突もありました。その隙間を埋め合わせないといけないのが、通訳の僕だったんです」
通訳は孤独だ。コーチ陣やマネージメント部門には複数のスタッフが配置されているのに対して、通訳は基本的に一人。誰にも悩みを共有できず、難しさを感じることも多かった。監督と常にいることも相まって、時には選手との距離が生まれてしまうことにも悩んだ。ただ、そういった壁を一つひとつ乗り越え、チームは’19年のラグビーワールドカップで史上初のベスト8に進んだ。これは格別の経験だった。
その経験を経た’20年、履正社専門で「スポーツ外国語学科」(当時)を立ち上げ、自ら学科長に就任。現在はGMとして学科に携わり、対面・リモートでの通訳講座や留学のカスタマイズをはじめ、学生に情熱的な指導を行っている。



ますます高まる英語人材の需要。
なぜ、佐藤は史上初のワールドカップベスト8進出という偉業の直後に、教育界への転身を決めたのか。
「通訳として働く中で、スポーツ業界の英語人材不足を間近に感じていました。僕は通訳の仕事と並行して、通訳を派遣する会社も経営しています。プロの現場から『即戦力はいないか』という相談はたくさんあるのですが、すぐに紹介できる人材が少ないことに問題意識がありました。そしてそれは通訳だけの問題ではありません。トレーナー、コーチ、スタッフなど、多くのスポーツ関係者にとって英語は必須になってきています。今や日本国内でも、世界で戦うのと近い環境になってきていると感じます」
現に、スポーツ業界は英語人材が不足している。国内プロリーグのグローバル化は進む一方だ。Jリーグ(サッカー)、Bリーグ(バスケットボール)、SVリーグ(バレーボール)、リーグワン(ラグビー)の監督・ヘッドコーチの外国人率は56%(2024年8月時点・男子1部リーグ)。2022年から12%も上昇している。特にラグビーでは、浦安D-Rocksや花園近鉄ライナーズなど、通訳を1人から2人、3人に増員したチームも多い。英語人材の需要は、ますます高まるばかりだ。
そして、どのチームも即戦力を必要としている。そんな人材を養成するために欠かせないのが、現場経験だ。外国語学科が持つ実習の受け入れ先は、佐藤の古巣であるラグビー・レッドハリケーンズ大阪やバレーボール・東レアローズ滋賀(女子チーム)、バスケットボール・大阪エヴェッサなど、関西を中心に競技は多岐にわたる。実際に卒業生の中には、この現場実習をきっかけに就職が決まった実績も生まれた。
また、2025年の2〜3月には、佐藤自身が育ったゴールドコーストに拠点を置くラグビークラブと、バスケットボールクラブへ学生2名を派遣。2020年の学科開設当初はコロナ禍で実現できなかった留学プログラムが、ようやくスタートした。佐藤は留学前の2024年夏にゴールドコーストへ帰り、クラブや学校機関、現地コーディネーターとの調整に奔走していた。それがようやく実った形になった。


「英語を話せるだけで、スポーツ業界で働けるわけではありません。専門知識やスキルも必要ですし、スポーツ現場ではどういうメンタリティやマインドセットが求められるのか、実践経験を積んで体得する必要があります。なので本校では、英語を使った実習やインターンシップを通じて、本場の現場知識、スキルはもちろん、人間力と感性を存分に磨いてほしいです。スポーツ業界はコネクションが物を言う世界。どこで、誰のもとで、どんな経験を積んだか。これが重要になります。『これだけ経験をしてきたので、即戦力としてすぐに貢献できます!』。そう言えるくらいに育ってほしい。自信を持って紹介できる人材を多く育てていきたいです」
現代ではAIの台頭もあって、さまざまな仕事の存在意義が問われている。通訳もその一つだろう。ただ、佐藤は言う。
「会話や情報交換はできたとしても、A Iに『気持ち』のやりとりはできないですよね。特にスポーツ通訳は、監督やコーチ、選手、その場で主語になる人の気持ちを汲まないといけない。だから、時には意訳したり、行間を読んだり、直訳を超えた情報伝達が多々必要になります。そういったノンバーバル(非言語)な部分の仕事は、AIにはできないと考えています」
第一線の通訳者、教育者として、佐藤の旅はまだまだ途中だ。2025年で開設6年目を迎える外国語学科からは、今後どんな人材が巣立っていくのだろうか。

佐藤 秀典 さとう・ひでのり
1981年、東京都生まれ。10歳でオーストラリアに移住し、現地の高校を卒業後、帰国して通訳の道に。2015、2019年のラグビーワールドカップで躍進したラグビー日本代表チームをはじめ、世界の大舞台を経験。「横浜キヤノンイーグルス」「レッドハリケーンズ大阪」などリーグワンでの通訳経験も豊富。2020年より、履正社国際医療スポーツ専門学校「外国語学科」(旧:スポーツ外国語学科)学科長に就任。現在は同学科GMを務める
写真/倉科直弘 文/中矢健太