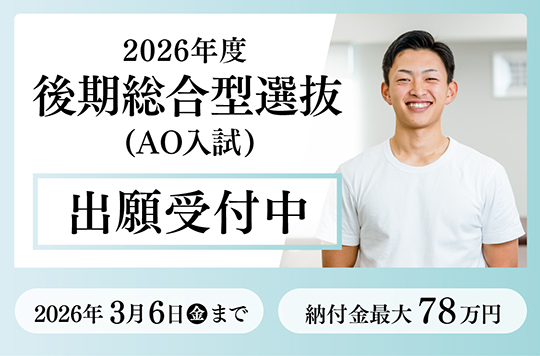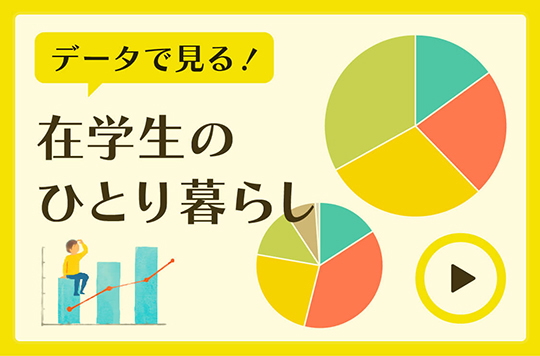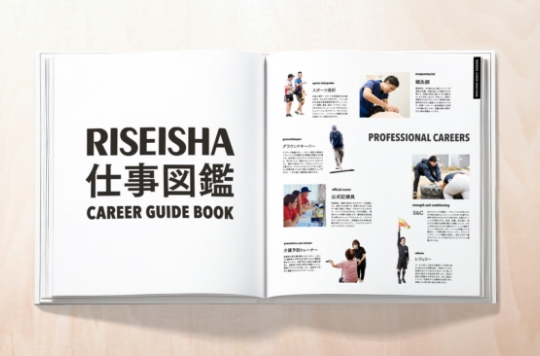こんにちは、タマノスケやで。
今日はな、「仲間の喜びが、自分のことみたいやった」っていう、そんな話を聞いてほしいねん。

⸻
大会の決勝。
タマノスケは、その日、ベンチやった。理由は、ケガ。
プレーできへん悔しさは、正直めちゃくちゃあった。
「最後の大会やのに、グラウンドに立たれへんなんて…」
そう思った瞬間、何回あったか分からへん。
でも、チームの一員であることに変わりはない。
せやから、誰よりも声を出して、必死に応援してたんや。
そして、試合は終盤。
9回裏、2アウト満塁。同点。
監督の声が響いた。
「ユウスケ、代打行けるか?」
「はい!」
同級生で、ポジションも似てて、ずっと張り合ってきたライバル。
誰よりも練習して、誰よりも声出して、チームの空気を引っ張ってきたやつ。
ほんまに泥くさくて、熱くて、まっすぐで――
タマノスケは、そんなユウスケの背中を、じっと見つめてた。
グラウンドに向かっていくその背中に、拳をギュッと握りながら、心の中でつぶやいた。
「頼んだぞ…ユウスケ」
⸻
カウントは2ストライク1ボール。
球場全体が静まり返る。息を呑む時間。
――カキーン。
打球は、鋭くライト前へ。走者がホームに返って、サヨナラ。
歓声が一気にグラウンドを包み込んだ。
ベンチもスタンドも、涙と笑顔であふれてた。
でも、タマノスケはその場で固まってた。
見えていたのは、ガッツポーズを決めるユウスケの笑顔だけやった。
その瞬間、なんでかわからんけど、涙が勝手にこぼれてきた。
「…やったな」
拍手も歓声も、聞こえへんくらい。
ただただ嬉しくて、胸の奥がグッとなった。
「なんでやろ…自分が打ったわけやないのに…
なんで、こんなに心が震えるんやろ…」
その答えは、ふと口から出た言葉に詰まってた。
「あいつの喜びが、自分のことみたいやってん」
⸻
試合が終わって、帰り道。
ユウスケが、ぽつりとつぶやいた。
「お前が一番喜んでくれてたの、ベンチから見えてたわ。
あんなん、めっちゃ泣きそうなった」
タマノスケは照れくさくて、笑ってごまかした。
「いや、泣いてたけどな。普通に。こっちは。」
⸻
昔の自分は、正直に言えば、
「なんで自分やないんや」って思ってたと思う。
「出たかった」し、「目立ちたかった」し、「ヒーローになりたかった」。
でも、この日だけは、ほんまに違った。
あいつのヒットが、自分のヒットより嬉しかった。
あいつのガッツポーズが、自分のホームランより誇らしかった。
それってきっと、もう「チームメイト」とか「ライバル」とか、そんな言葉やなくて。
本気で支え合ってきた“仲間”になれてたからなんやと思う。
⸻
仲間ってな、悲しいときに寄り添ってくれる存在やけど、
「嬉しいときに、心から一緒に喜べる存在」でもあるねん。
自分が悔しいときに、一緒に泣いてくれて、
自分がうまくいかんときに、背中押してくれて、
そんで、誰かが輝く瞬間に、自分のことのように喜べる。
それが、“ほんまもんの仲間”なんちゃうかな。
⸻
その夜、布団に入ったタマノスケは、ふとつぶやいた。
「また、あいつと野球したいな」
ユウスケと一緒にグラウンドを駆けまわった時間。
泣いたことも、笑ったことも、全部がタマノスケの宝もんや。
たとえ今は別々の道を歩いてても、
「喜びを分かち合える仲間」って、一生もんや。
この先、どんな道を選んでも、
あの日の気持ちを、ずっと胸に持っていたいと思ったんや。
⸻
仲間って、やっぱり最高やな。
タマノスケより。